ニュース;
青紫レーザー 究極の「青」はどうやって実現された? |
|
 |
青色LED&レーザーの開発は、日本の小さな企業の研究員だった中村修二氏によってほとんど完成された。しかし、風変わりな研究スタイルや逸話、昔の勤め先である日亜化学との特許裁判など、サイドストーリーばかりが有名になってしまった一方で、その実現がどれだけ困難だったかを知る機会はあまりない。…
|
|
| ICチップができるまで |
|
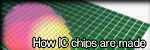 |
例えばあなたの使っているIntelのPentium
IVのマイクロプロセッサには、トランジスタが4600万個も含まれている。手のひらに載る程度のチップにそれだけ多くの数のトランジスタが詰まっていることなど、とても想像できそうにもない。
ICの製造過程は、ウエハを用意してからチップが出来あがるまでだけでも300-500ステップほどあり、回路の設計やパッケージングなどまで含むと莫大な数のステップになる。
|
|
| 半導体 |
|
 |
導体、半導体、絶縁体の本質的な違いとは?この三つを区別する一つの目安に「抵抗率」というものがある。図にあるように、よく電気を通すものを「導体」、ほとんどあるいはまったく電気を通さないものを「絶縁体」、そして、その中間にあるのが「半導体」という具合だ。 |
|
| トランジスタ |
|
 |
トランジスタは現在のエレクトロニクス製品のほとんどに含まれており、重要な基礎を成している。またコンピュータの基本的な機能、例えば論理式・数式の評価、情報の蓄積などもトランジスタ一つ、もしくは複数から構成されている。 |
|
| 論理ゲート |
|
 |
電子計算機の様々な計算・判断それに記憶は、どのようにして行われているのだろうか?そういった処理は「論理回路」と呼ばれる部分によって実行されている。論理回路が基礎を置いているのは、19世紀のイギリスの数学者ブール(George
Boole)が考え出した「ブール代数」というものだ。それによると、理論表現は「真(TRUE)」または「偽(FAULSE)」のどちらかをとらなくてはいけないという。しかし考えてみれば、この二つの表現から出発し、あれほど複雑な処理が可能になるとは、にわかに信じがたい。 |
|
| アモルファスシリコン&ポリシリコン |
|
 |
シリコンのような無機結晶の半導体は、規則正しい構造がほとんど無限に繰り返されている。半導体に電気が流れるとき、その規則正しい結晶構造のなかを電子が移動する。
ところが「アモルファスシリコン(a-Si;amorphous
silicon)」、「ポリシリコン(多結晶シリコン、p-Si;polysilicon)」は、こういった規則正しい構造を持たず、単結晶のシリコンにないようなユニークな性格が現れてくる。応用でもTFT液晶ディスプレイ、太陽電池と、単結晶シリコンと違ったところで活躍している。 |
|
| 半導体メモリ |
|
 |
一口にメモリと言っても様々なタイプのものがある。例えば「パソコンのメモリが128M,256M…」などということがあるが、これは「ランダムアクセスメモリ(RAM;Random
Access Memory)」のことだ。PDAやデジカメなどで使っているメモリは「フラッシュメモリ(Flash
Memory)」というもので、同じ半導体メモリでもRAMとはずいぶん性格が異なる。 |
|
| 発光ダイオード、LED |
|
 |
あたりを見回していると人工的な光はいくつも見当たるが、電気がもとになっている光にはどんなものがあるだろう?まず間違いなく、白熱灯が目に入る。蛍光灯もそうだろう。この二つに関しては、どこに行っても見ないことはない。ただ、他にも必ず見るものはないだろうか?そう、「発光ダイオード(LED,light
emitting diode)」だ。 |
|
| 半導体レーザー |
|
 |
光ファイバーなどの情報通信をはじめ、CDやDVDのデータストレージ、それに医療、鉄の切断などレーザーの応用範囲は実に広い。
そもそもレーザーの光と普通の光というのはどう違うのだろう?ちゃんと説明できるだろうか?どうして散乱せずにあれだけ明るい単色光が可能なのだろう?それにレーザーにはどのようなタイプのものがあるのだろう?鉄を切断するレーザーとCDプレイヤーのレーザーとではどう違うのだろう? |
|
| ハードディスク |
|
 |
コンピュータ業界には集積回路の成長を予測するムーアの法則というものがあり、この業界を支える重要な柱となっている。その内容は18カ月で集積回路の性能がだいたい2倍になるというものである。
一方、ハードディスクについても同じように年を追うごとに面記録密度が上昇してきたが、こちらの場合は徐々にそのペースが速くなってきている。いや最近では、「徐々に」というより、「急激に」速くなっている。 |
|
|