有機ELディスプレイ
− 有機ELの量子効率について
アカデミックな意味でも、そして商品としての意味でも、有機ELの「効率」というものは重要な関心事になってくる。ただし、その「効率」というのは、使う場所によって意味合いが異なってくるし、当然その数値結果も異なってくる。
有機ELでは、数あるタイプの効率のなかで、「内部量子効率(internal quantum efficiency)」と「外部量子効率(external quantum efficiency)」がよく使用される。そこでこのページでは、この2つの量子効率の意味と、どうやってこの効率を高めることができるかについて考えてみることにしよう。
内部量子効率、外部量子効率とは
有機ELの効率について、いくつかのステップに分けて考えてみよう。
電子と正孔が再結合すれば必ず光子を外部に放出するとしても、消費電力がすべて光エネルギーとして得られるわけではない。なぜなら、電源から供給された電子と正孔がすべて再結合できるとは限らないためだ。再結合せずに、オーム抵抗によって熱として失われてしまう部分があるはずだ。
次に、注入された電子と正孔が再結合したからといって、それが必ず光子を生み出すとは限らない。再結合しても光としてエネルギーを放出せずに、エネルギーの一部を熱として放出する場合があるからだ(ほとんどの場合がそうだが)。注入されて再結合した電子の数に対して生み出された光子の割合を「内部量子効率(internal quantum efficiency)」とよぶ。励起エネルギーが光に変換した割合と表現することもできるだろう。
さて、光子が生み出されたからといって、その光子が私たちの目に必ず飛び込んでくるとは限らない。生じた光子は、有機ELチップ(サンドイッチ構造の部分)の内部で、境界面での全反射により外部に出てこない場合もある。有機ELチップ内で生じた光子の数に対し、外部に出てくる光子の数の割合を「光取り出し効率(light-extraction
efficiency)」とでも呼ぶとしよう。
「外部量子効率(external quantum efficiency)」というのは、内部量子効率に、この光取り出し効率を考慮したものだ。
スネルの法則ではガラスと空気の全反射角は43°で、プラスチックの場合も大体そのくらいの値である。そのため有機層で発生した光の80%ちかくが内部に閉じ込められて外に取り出すことができない。このように光取り出し効率は極端に低いため、内部量子効率と比べて外部量子効率はずいぶん小さくなる。実際の外部量子効率は高くても10%程度である。
 「量子収率(quantum yield)」と「量子効率(quantum
efficiency)」の定義について 「量子収率(quantum yield)」と「量子効率(quantum
efficiency)」の定義について
蛍光とりん光(燐光)
電子と正孔が再結合しても、(可視光範囲の)光を必ず発するとは限らない。励起した電子が再び基底状態に戻ることで光が放出されるが、そのときの過程によっては、光ではなく熱としてエネルギーを放出してしまうこともあるのだ。
一般に、光を放出するAの道順を「蛍光(fluorescence)」、可視光をださずに熱としてエネルギーを放出するBの道順を「りん光(phosphorescence)」という。有機ELでは、蛍光を利用することになる。
キャリアの再結合により生成する励起状態には、「一重項状態(singlet)」と「三重項状態(triplet)」があるが、一般的な有機色素の場合、室温においては励起三重項状態からの発光(りん光)は観測されないので、励起一重項状態からの発光のみが観測されることになる。
下図にそれぞれの過程についての説明を示した。
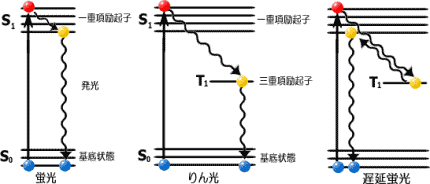
蛍光、りん光、遅延蛍光の過程を示すJablonskiダイアグラム
A.蛍光;再結合によってエネルギーを得た電子は、一重項励起子の最もエネルギーレベルの高いところへ移る。そして、一重励起子でエネルギーレベルの高いところから低いところに移り、一気に基底状態まで戻る。このときに可視光を出す。これら一連の過程は1ナノ秒以下という非常に短い時間でおこる。
B.りん光;途中までは蛍光と同じだが、一重項励起子から直接基底状態に戻るのではなく、いったんエネルギーレベルの低い三重項励起子に移る。そして三重項励起子から基底状態に戻るので、発する光の波長が蛍光のときより長い。そのため可視光は出さない。三重項励起子にある時間は1ミリ秒から1秒程度と比較的長い。
C.遅延蛍光;三重励起子から再び一重励起子にあがり、そこから蛍光を発する。蛍光、りん光がナノスケールで終了するのに対し、遅延りん光は秒、分といった長いスケールで現象が起こることも珍しくない。 |
ところで量子物理化学からは、統計的に、三重項励起子と一重項励起子の発生割合は3:1であることが分かっている。したがって、一重項励起子の蛍光だけに頼っていては、内部量子効率は最高25%ということになってしまう。もちろん外部量子効率は内部量子効率より低く、10%以下が普通である。
リン光発光材料を利用した有機EL
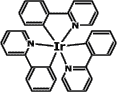 しかし、98年に米プリンストン大学のBaldoら(発見当時は大学院生だった)によって、希土類金属を含むりん光発光材料が存在している場合、りん光が蛍光とハイブリッド状態になり、可視光を放出することがわかった[1]。そのとき使われたりん光発光材料は、Ir錯体である"iridium
polypropylene (Ir(ppy)3)" (左図)だった。 しかし、98年に米プリンストン大学のBaldoら(発見当時は大学院生だった)によって、希土類金属を含むりん光発光材料が存在している場合、りん光が蛍光とハイブリッド状態になり、可視光を放出することがわかった[1]。そのとき使われたりん光発光材料は、Ir錯体である"iridium
polypropylene (Ir(ppy)3)" (左図)だった。
そのとき提案されたサンドイッチ構造ではIr(ppy)3の発光寿命が短いため実用化は難しいが、この発見に刺激されて、世界中でIr(ppy)3を使った有機ELの研究が行われている。
これによって単純に考えれば、内部量子効率の上限は100%ということになる。このりん光発光材料を使って有機ELディスプレイを研究開発しているのは、米ユニバーサルディスプレイコーポレーション(UDC)(ソニーの有機ELはUDCと共同開発している)などがある。
これまではりん光を利用した有機ELは低分子のものが中心だったが、最近ではNHK技研などが高分子などでも実現している。(プレスリリース)
また、りん光発光材料をドーピングした場合、長寿命な有機ELディスプレイを製造できることも期待されている(詳しくは「今後の課題・展望」を参照)。
ref.
[1]Nature 395, 151 - 154 (1998) M.
A. BALDO et al.
|
|