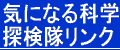大腸菌の「分子モーター」。大腸菌の細胞膜には、非常に精巧な分子モーターが秘められています。約256個の水素イオンの流入で鞭毛が一回転すると考えられています。 大腸菌の「分子モーター」。大腸菌の細胞膜には、非常に精巧な分子モーターが秘められています。約256個の水素イオンの流入で鞭毛が一回転すると考えられています。
|

 ミトコンドリアの「分子モーター」についての実験。(説明左)※なお、a,b,cといったタンパク質の相対的な位置関係についてはまだハッキリしていないので、この図の位置関係が正しいとは限りません。 ミトコンドリアの「分子モーター」についての実験。(説明左)※なお、a,b,cといったタンパク質の相対的な位置関係についてはまだハッキリしていないので、この図の位置関係が正しいとは限りません。 |
大腸菌は見た目の通り、この上なく簡単な仕組みをしているように思えます。確かに生物としては非常に単純なのですが、それでもナノの視点から眺めると、驚くべき仕組みが隠されています。大腸菌には長い鞭毛があり、それを回転させることで運動を可能にしているのですが、この鞭毛はどういった仕組みで動いているのでしょうか?
一般に大腸菌の細胞膜の内側と外側では水素濃度が大きく異なります。そのため内膜を挟んで電位差が生じ、水素イオンが流れ込むという駆動力が生じます。大腸菌を含め多くの細菌は、この水素イオンの駆動力により、ATP合成酵素によるADPからATPへの生成や、無機イオンの輸送、そして鞭毛の回転などを可能にしているのです。
まさに、大腸菌の細胞膜に埋め込まれたこの十数ナノメートルの仕組みは、細胞内に存在して回転力を得る「分子モーター」といえるのです。
従来なら、いくつかのタンパク質によって構成された系で、「回転」が得られるなどということは考えにくいものです。しかし、人間が手を加えて、実際に「分子モーター」が回転していることを以下の方法で確認し、本当に回転していることが証明されたのです。
----------------------------
利用したのは、真核生物の細胞内でエネルギーをつくっているミトコンドリアの細胞膜に埋め込まれた「分子モーター」でした。
これはミトコンドリアのATP合成酵素の構造モデル図です。普段はa,b,cといった下部を水素イオンが流れ込み、その駆動力によって軸γが時計回りに回転します。こうして上部が回転します。その際に、βの部分でADPからATPが生成されます。こうして、生物が生きていくのに必要なATPがつくられます。
一方で、β部分でATPがADPに分解されれば、γ軸は反時計回りに回転し、結果として下部も反時計回りに回転すると考えられていました。こうして内部の水素イオンをくみ出すポンプのような役割をするわけです。
ただし、これが回転しているのを確認しようとすると、当然タンパク質が「生きて」いなくてはいけません。電子顕微鏡やX線結晶解析といったタンパク質を「殺して」しまう方法は取れません。基本的には光学顕微鏡を使わなくてはいけませんが、十数ナノメートルの分子モーターを見ることは出来ません。そこで工夫が必要です。
そこで、上部だけをミトコンドリアから外して、γ軸の先に棒状の数千ナノメートル(数マイクロメートル)アクチン繊維を取り付けました。
今回の場合は、下部で生じる水素イオンの駆動力がないので、上部のβ部分によるATP→ADPへの分解が一方的に行われます。したがって、アクチン繊維も反時計回りに回転するはずです。
・・・結果は、本当にアクチン繊維が反時計回りに回転していました。これによって、タンパク質が本当に回転することが証明されたのです。
また、分子モーターのようなナノスケールのデバイスには、ブラウン運動の影響を避けることはできません。実際分子モーターはこの無秩序なブラウン運動を巧みに利用して、方向性のあるエネルギーを取り出しているのです。詳しくは気になる科学ニュース「マクロスケールの常識を覆す分子モーター」を参考。
この分子モーターは細胞の未だに分かっていない仕組みを研究させるのに役立つだけでなく、将来的にはナノテクノロジーによって、「ナノマシーン」などの駆動力となるかもしれません。 |
-アイコンの説明-
 ・・・「気になる科学ニュース調査」からの関連記事です。 ・・・「気になる科学ニュース調査」からの関連記事です。
 ・・・「こちらは気になる科学探検隊」の外部へのリンクです。 ・・・「こちらは気になる科学探検隊」の外部へのリンクです。
 翻訳サイトの紹介が別ウィンドウで開きます。 翻訳サイトの紹介が別ウィンドウで開きます。
|